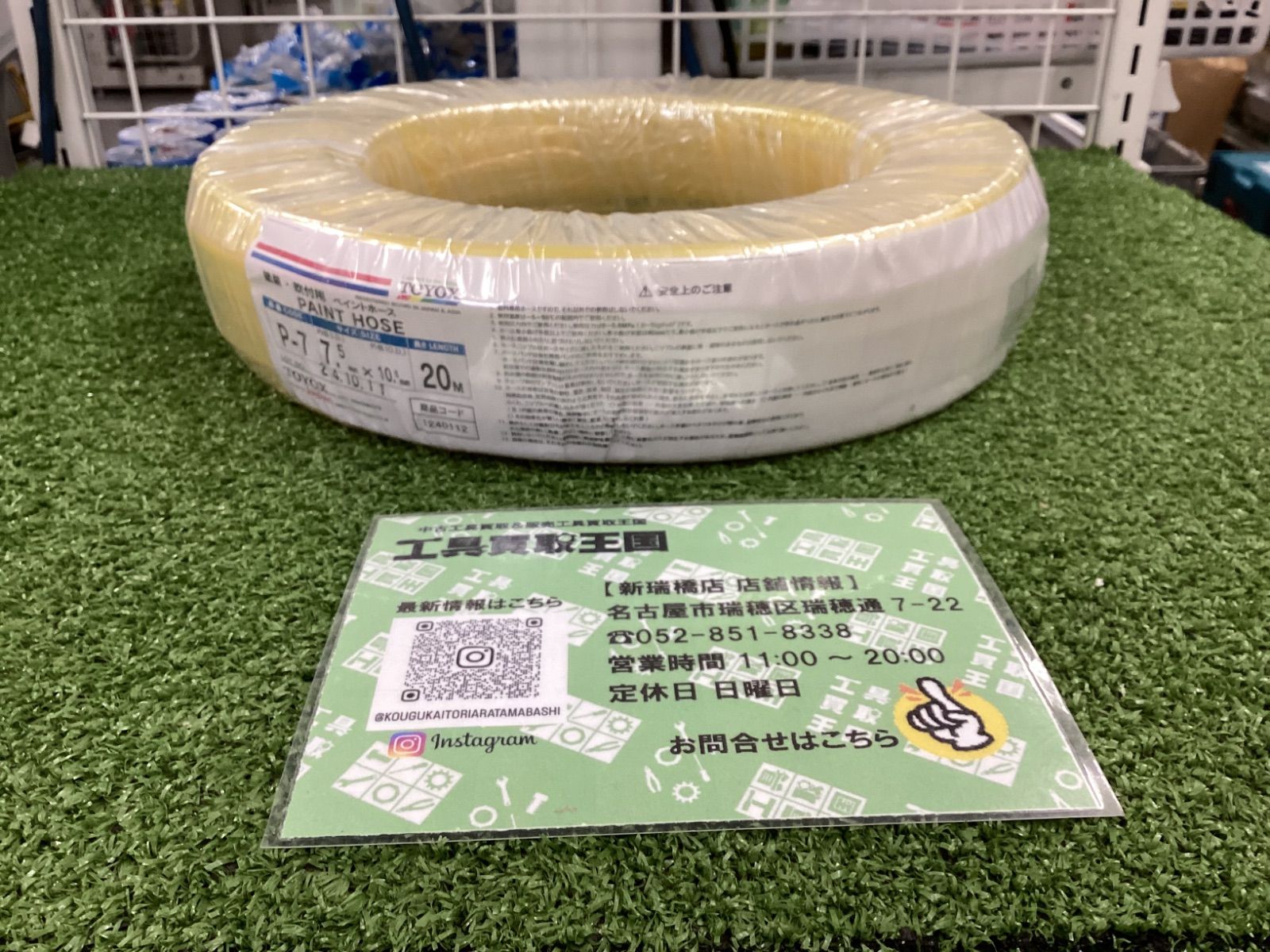マイストア
変更
お店で受け取る
(送料無料)
配送する
納期目安:
08月02日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
要相談 275 紳士用 大島のアンサンブル新品、♥ 【安心の国内正規商品】 の詳細情報
鈍い青緑がかった藍色の一元式絣で織られた120亀甲の大島のアンサンブルです。
一元(ひともと)式とは、タテ糸2本、ヨコ糸2本を交差させて風車のような井型の絣模様を作る織り方です。
亀甲数が多くなればなるほど絣が細かくなりますが、小さすぎると亀甲に見えないと思っておられる方もいらっしゃるようです。
細かな亀甲柄は織る方も少なく、コスト高になることもあってか100亀甲が主流のようです。
一般的に120亀甲といえば普通巾(1尺:約38cm)の場合、120個並ぶというのが当然のようですが、120前後であれば120亀甲とされているようです。
出品します大島は120亀甲で亀甲数を数えますとアバウトですが125の計算になるかと思います。(写真8枚目38cmの10分の1で撮影)
亀甲文様は、飛鳥時代から奈良時代にかけて、中国から日本に伝来しました。
当時の中国では、亀の甲羅を使って、政策決定や意思決定を行う、亀ト(きぼく)と呼ばれる占いが広く行われていました。
亀トは、長時間にわたって亀の甲羅を焼いて、甲羅の表面に入ったひび割れの方向、形状を見て、物事の吉凶を判断するものです。
上記のような理由から、亀の甲羅を模した亀甲文様は、中国国内においては、とても神聖なものとして扱われた、と言われています。
着物裏地は綿のカネキンの葡萄の色を鼠がからせた鈍い赤紫の葡萄鼠(ぶどうねずみ)に似た色目を使用しています。
羽織裏は渓谷に佇む民家や滝から流れる渓流にかかる橋で釣りをする人を描いた正絹の羽二重友禅です。
寸法(単位㎝)
身丈(背)144,5 裄68 袖巾34 袖丈49 後巾30 前巾26,5
羽織丈93 裄69
体形にもよりますが、身長176cm位の方ですと足のくるぶし真ん中辺りに着物の裾が達する様です。
仕付け糸付きで汚れは無いようです。
シミ汚れ等は出来る限りチェックしておりますが、見落としのある場合もございます。ご理解のほどお願いいたします。
デジカメの画像です。モニターによって色の違いが出ることがありますので、ご了承ください。
写真9~11枚目の表地と16枚目の羽織裏の羽二重組織の拡大写真はUSBマイクロスコープ顕微鏡でで写しています。
撮影に使用しました羽織紐と角帯は今回の出品物ではありません。
一元(ひともと)式とは、タテ糸2本、ヨコ糸2本を交差させて風車のような井型の絣模様を作る織り方です。
亀甲数が多くなればなるほど絣が細かくなりますが、小さすぎると亀甲に見えないと思っておられる方もいらっしゃるようです。
細かな亀甲柄は織る方も少なく、コスト高になることもあってか100亀甲が主流のようです。
一般的に120亀甲といえば普通巾(1尺:約38cm)の場合、120個並ぶというのが当然のようですが、120前後であれば120亀甲とされているようです。
出品します大島は120亀甲で亀甲数を数えますとアバウトですが125の計算になるかと思います。(写真8枚目38cmの10分の1で撮影)
亀甲文様は、飛鳥時代から奈良時代にかけて、中国から日本に伝来しました。
当時の中国では、亀の甲羅を使って、政策決定や意思決定を行う、亀ト(きぼく)と呼ばれる占いが広く行われていました。
亀トは、長時間にわたって亀の甲羅を焼いて、甲羅の表面に入ったひび割れの方向、形状を見て、物事の吉凶を判断するものです。
上記のような理由から、亀の甲羅を模した亀甲文様は、中国国内においては、とても神聖なものとして扱われた、と言われています。
着物裏地は綿のカネキンの葡萄の色を鼠がからせた鈍い赤紫の葡萄鼠(ぶどうねずみ)に似た色目を使用しています。
羽織裏は渓谷に佇む民家や滝から流れる渓流にかかる橋で釣りをする人を描いた正絹の羽二重友禅です。
寸法(単位㎝)
身丈(背)144,5 裄68 袖巾34 袖丈49 後巾30 前巾26,5
羽織丈93 裄69
体形にもよりますが、身長176cm位の方ですと足のくるぶし真ん中辺りに着物の裾が達する様です。
仕付け糸付きで汚れは無いようです。
シミ汚れ等は出来る限りチェックしておりますが、見落としのある場合もございます。ご理解のほどお願いいたします。
デジカメの画像です。モニターによって色の違いが出ることがありますので、ご了承ください。
写真9~11枚目の表地と16枚目の羽織裏の羽二重組織の拡大写真はUSBマイクロスコープ顕微鏡でで写しています。
撮影に使用しました羽織紐と角帯は今回の出品物ではありません。
カテゴリー:
ファッション##メンズ##着物・浴衣
商品の状態:
新品
配送料の負担:
送料無料
配送の方法:
らくらくメルカリ便
発送元の地域:
京都府
発送までの日数:
2~5日
ベストセラーランキングです
近くの売り場の商品
カスタマーレビュー
オススメ度 4.4点
現在、4744件のレビューが投稿されています。